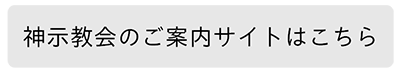「三立の儀」で我が子を育む思いが強く
夫婦で心温まる家庭を
「はえば立て、立てば歩めの親心」。我が子の成長を心待ちにし、「健康で、仕合せな人生を歩んでほしい」と願うのが、親というもの。そのために、“どんなことでもしたい!”と試行錯誤する人も多いでしょう。
子供がどう育っていくか、そこに最も影響するのが「家庭」です。心と体と魂で成る人間は、その“調和”が大事。心の自制が利かない幼子も、親の愛情を感じていくところに、魂が安定していきます。そうした家庭であれば、温かく優しい心が育まれて、心身ともに伸びやかに成長していけます。
親子で過ごした年月を振り返り、3歳、5歳、7歳の節目を祝う「三立の儀」(七五三)。成長した我が子の姿に、親としての心が強く引き出されるこの儀式が、神総本部と全国の偉光会館で行われています。

両親の間にちょこんと座る子供たち。もじもじしたり、パパやママの顔をのぞき込んだり。愛くるしい姿を、家族みんなが優しく見守る中で儀式が始まります。
まず、伝導師が、無事に節目を迎えられた御礼を、神に申し上げます。ひと言ひと言をかみしめながら、感無量の面持ちになる親御さんたち。初めておしゃべりした時、歩いた時、熱を出した時。家族で過ごしたさまざまな場面が思い出され、健やかな成長に感謝が深まります。

神に、直接思いを届ける神飾り奉奠(かんかざりほうてん)。大切な我が子を、親として責任を持って育てる決意を祈願。幼子も一緒に手を合わせて。(茨城高萩偉光会館)
儀式を通して、父母の心に膨らむのは、自分を育んでくれた両親の愛情です。「人一倍泣き虫な私が頑張れたのは、いつも親が温かく寄り添ってくれていたから。その優しさが、いまさらながら染みました」「きかん坊で、手が掛かる子供だった私。それでも、丸ごと受け止めてくれた親心の大きさが、息子を持った今なら分かります」。親からもらった愛を、惜しみなく我が子へ。各人が、ますます愛情たっぷりに子供と向き合っていくことを誓いました。
最後は、お子さんから親御さんに、感謝を届けます。「お父さん、お母さん、いつもありがとう!」。普段と違う我が子の堂々とした姿に、目を丸くする家族も。自閉症で、うまく言葉にできない子は、母親の膝に顔を埋めて、全身で「ありがとう」を表現。思い思いの感謝が伝わって、どの家族にも笑顔がこぼれ、どんどん親子の絆が強まっていきます。

無事に儀式を終えると、誰もが明るく、ホッとした表情に。「おめでとう!」「ちゃんとご挨拶できてたね」という言葉に、得意げな子供たち。会話が弾む中、儀式でもらったお菓子を兄弟に分けてあげる姿も。両親は、和やかな家族の様子に目を細めながら、親としての新たな決意を口々に語っています。
「この3年、無事に育てられたのは、たくさんの支えがあったから…と、心からの感謝が湧き上がりました。一番は妻。子供と私にちゃんと向き合ってくれて…。お互いにゆとりを欠くことがあるので、そんなときこそ夫婦で語り合い、我が子に愛を注げる私たちでありたいです」
「7歳の娘は障害があり、子供の気持ちをうまくつかめなくて大変と思ったこともあります。でも、この子の笑顔から、親としての喜びをどれだけもらっているか。明るくて、愛嬌(あいきょう)があって、みんなに愛されて…。そんな良さを誰よりも知っているのは、私たち。娘の長所を目いっぱい伸ばしていきたいと思えたら、すごく力が湧いてきました!」
「『我、子の親と今なりて、深き父母の愛をば思わん…』神歌を聞きながら、私が子供だった頃も、今も、親はずっと愛をかけ続けてくれていると、両親への感謝が込み上げて涙があふれました。『子育て、もっと頑張らないと!』と気負う私に、『もう十分頑張っているから』と優しく言ってくれた母。その言葉に、スッと気持ちが楽になったんです。いつでも受け止め、愛してくれる母のように、私もなりたい! その心が強く強く持てました」
「みんな元気で、たくましく、相手を気遣える子に育っていることがうれしい」と語るのは、3歳、5歳、7歳の子を育てる女性。ご主人も、「子供たちには、思いやりの心を育んでほしい。そのお手本を見せていける夫婦を目指します」と思いを語っていました。

夫婦の心を一つにし、温かい家庭を築く…。この誓いを実行に移すごとに、夫婦の絆も、親子の絆も深まり、家族で味わう仕合せも増すことでしょう。心温まる家庭では、我が子の潜在能力が確実に芽吹きます。15歳を迎える頃には、心と体と魂がバランスよく保たれ、自身の力をもって人生を力強く歩み出せる! その時を楽しみにしましょう。
写真追加(7.11.22)
写真追加(7.12.4)
写真追加(8.1.26)
※儀式は、いつでも希望に合わせてお申し込みいただけます。
親子で一緒に学ぶ、小、中学生対象の勉強会「実りの集い」や、どのような心で子育てをすればよいのか、親の心をつかむ場もあります。ぜひ、ご活用ください。